日本の複式簿記の導入
日本で複式簿記が導入されたのは、以外に新しく、明治時代
になってからのことです。
明治6年6月福澤諭吉がアメリカの簿記教科書『コモン・スクール・
ブックキーピング』という本を翻訳し日本初の簿記書である
『帳合の法』初編を出版しました。
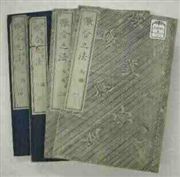
この本はただの訳書ではなく、日本に新しい企業精神を芽生え
させたいとの福沢諭吉の思いが詰まっていたと言われています。
またこれに続き、10月には加藤斌(たけし)の『商家必用』、12月に
大蔵省の『銀行簿記精法』と、西洋式簿記書が相次いで刊行され、
洋式簿記の導入が始まりました。
日本の複式簿記の導入は、銀行や官庁を皮切りに、始まりましたが、
これは商人の自発的必要性から発生した西洋と違い、政府が民間
(特に財閥)に対して徴税を目的に決算内容の報告を義務付けた
ことから発展したと言われています。
になってからのことです。
明治6年6月福澤諭吉がアメリカの簿記教科書『コモン・スクール・
ブックキーピング』という本を翻訳し日本初の簿記書である
『帳合の法』初編を出版しました。
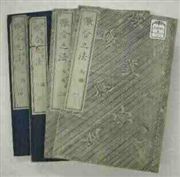
この本はただの訳書ではなく、日本に新しい企業精神を芽生え
させたいとの福沢諭吉の思いが詰まっていたと言われています。
またこれに続き、10月には加藤斌(たけし)の『商家必用』、12月に
大蔵省の『銀行簿記精法』と、西洋式簿記書が相次いで刊行され、
洋式簿記の導入が始まりました。
日本の複式簿記の導入は、銀行や官庁を皮切りに、始まりましたが、
これは商人の自発的必要性から発生した西洋と違い、政府が民間
(特に財閥)に対して徴税を目的に決算内容の報告を義務付けた
ことから発展したと言われています。
★簿記について知っておこう
┣簿記の歴史┣簿記3級でできること
┣簿記3級の基本の基本
┗簿記についてのよくある質問について
★簿記3級合格に向けて
┣簿記3級検定試験の概要┣筆記用具の準備
┣簿記通信講座か独学かを決める
┣簿記通信講座で簿記3級合格を目指す
┣簿記の通信講座なら大原がおススメです
┣独学で簿記3級合格を目指す
┣簿記の基礎
┣簿記3級合格のためのおススメテキスト
┣簿記3級の勉強法
┣試験直前攻略法(最後の3日で勝負が決まる)
┣試験当日の過ごし方
┗勉強苦手な私の秘密兵器=リバース学習法)
★キャリアプラン診断
┗キャリアプラン診断シート★相互リンク歓迎
┣相互リンク歓迎┗相互リンクトップページ
